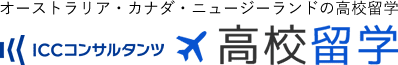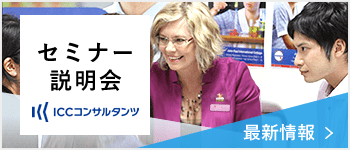日本の大学へ進学する
海外の高校を卒業後、日本の大学へ進学する方法としては、主に「一般選抜(一般入試)」「帰国生対象入試」「総合型選抜(旧AO入試)」の3つがあります。自分の進路や学力、志望校に合わせた受験方法を選ぶことが重要です。
一般選抜(一般入試)
海外の高校を卒業していれば、日本国内のほとんどの大学・学部の一般選抜を受験する資格があります。ただし、日本の高校生と同じ範囲での学力試験が課されるため、日本の教育課程に対応した受験勉強が必要です。帰国後すぐの受験は難しい場合もあり、1年間の浪人期間を設けて学び直すケースが多く見られます。
帰国生対象入試(帰国生入試)
帰国生入試は、海外で一定期間教育を受けた生徒のために設けられた入試制度です。海外での教育経験や語学力、国際的な視野などが評価される傾向にあり、留学の経験を活かした入試が可能です。
受験資格は大学ごとに異なるものの、「最終学歴が海外の学校であること」「一定期間海外に滞在していたこと」などが一般的な条件です。選考方法は、書類審査、小論文、面接、英語試験などが中心で、一般選抜とは異なったアプローチで受験できるのが特徴です。出願資格や内容は大学・学部により異なるため、事前の情報収集が不可欠です。
総合型選抜(旧AO入試)
現在の「総合型選抜」は、以前のAO入試にあたる制度で、出願者の人物像や意欲、適性などを重視して選考が行われます。成績だけではなく、志望理由書、課外活動実績、プレゼンテーション、面接などを通して総合的に評価されます。
「大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)」と応募者の自己PRがマッチしているかどうかがカギとなるため、自分の個性や留学経験を活かしたアプローチが可能です。現在では多くの大学で導入されており、受験方法の一つとして広く認知されています。
オーストラリア&ニュージーランド留学生の帰国生受験パターン
オーストラリアやニュージーランドでは、学年の終了が通常12月上旬となるため、日本の大学入試日程との調整や注意が必要です。帰国生入試は欧米型の学期に配慮して行われることが多いものの、大学ごとに時期や出願方法が異なるため、早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
ここでは、海外の高校から日本の大学進学を目指す際に考えられる代表的な受験パターンをご紹介します。
一時帰国で受験する
私立大学の多くは9~11月ごろに帰国生入試を行います。オーストラリアやニュージーランドに留学している場合は、在籍高校の許可を得て、2~3週間程度の休暇をとり、日本に帰国して志望大学の入試を受けます。
- 志望校や志望学部が明確であり、受験準備が進んでいる学生におすすめ
- 出願締切や必要書類の準備には特に注意が必要
現地の高校を卒業後に受験する
現地校を卒業後、12月〜翌年1月に実施される入試を受験するパターンです。願書提出や出願は現地にいる間に済ませ、卒業後に帰国してすぐ受験する必要があります。
- 卒業直後の受験になるため、早い段階からの学習スケジュール管理がカギ
- 出願書類の準備と締切スケジュールは事前確認を徹底
秋季入学の大学を選ぶ
一部の大学では、秋入学(9月入学)制度を導入しており、学期のズレに対応しやすくなっています。これらの入試では、書類審査中心で合否を判断する大学もあります。
- 出願時期が春~初夏であることが多く、卒業後の進路計画に余裕ができる
- 学業成績、統一試験(例:IB, NCEA, ATAR など)、推薦書の内容が重視される場合がある。
準備期間を設けて翌年受験する(いわゆる“ギャップイヤー”)
志望校や専攻したい分野がはっきりしていない、大学で何をしたいのかわからない、あるいは志望校は決まっていても受験態勢が万全ではないなど、受験・進学に対して不安のある人は、1年間の準備期間を設けて翌年の受験に挑戦するという選択肢もあります。
- 受験勉強に集中でき、志望校選びや出願準備も余裕を持って進められる
- 帰国生入試の多くは「帰国後2年以内」が出願資格の目安なので、志望大学の条件は要確認
カナダの留学生の帰国生受験パターン
カナダの高校では、地域により若干異なるものの、多くが6月下旬に学年が終了します。これにより、日本の大学入試スケジュールとの調整が比較的しやすい反面、卒業証明や成績証明の発行時期、書類準備には注意が必要です。また、カナダにはセメスター制を導入している学校も多く、履修科目や単位の記録方法も大学によって確認が必要です。以下に、日本の大学進学を目指す際に考えられる代表的なパターンを紹介します。
一時帰国で受験する
多くの私立大学では9~11月ごろに帰国生入試を実施しており、カナダの学校に在籍中でも一時帰国して受験することが可能です。休暇期間中(サンクスギビングや冬休み)を活用したり、学校から許可を得て数週間の帰国を計画するケースもあります。
- 志望大学の入試日程に合わせて計画的な一時帰国が必要
- SAT・IELTS・TOEFLなど、外部試験のスコア提出も忘れずに
- カナダの高校の協力を得て、在学証明や成績証明を早めに準備
現地の高校を卒業後に受験する
6月に卒業後、帰国して7月~翌年1月にかけて実施される帰国生入試や一般入試に挑戦するパターンです。必要書類の準備を在学中に済ませておく必要があります。
- 高校卒業と帰国生入試が比較的スムーズに接続できる
- 卒業証明書・成績証明書の取得時期や書類形式を大学ごとに要確認
- 一般選抜(2月以降)に挑戦するケースもあり得る
秋季入学の大学を選ぶ
9月入学を受け入れている日本の大学や学部では、カナダの卒業時期とスムーズに接続可能です。出願時期は春〜夏が多く、書類選考中心の入試も多いため、準備計画が立てやすくなります。
- 学業成績や卒業資格、英語能力試験スコアの提出が求められることが多い
- 卒業から進学までの空白期間を減らせる
- 英語力が高い生徒には特におすすめ
準備期間を設けて翌年受験する(いわゆる“ギャップイヤー”)
帰国後1年間を準備に充て、翌年の受験に挑むパターンです。進路に悩んでいる、志望校の対策が十分でない場合に有効で、英語力を維持しながら受験勉強に集中できます。
- 自分の志望や適性を見極める時間が取れる
- 多くの大学で「帰国後2年以内」の出願条件を満たせる
- ギャップイヤー中の活動(学習、ボランティア、インターンなど)もアピール材料になる場合がある
帰国生入試とは
それでは、帰国生枠の入試というのは、どういったものなのでしょうか。受験書類や必要書類からその特徴をみていきましょう。
受験資格(※大学によって条件が異なります)
以下は一般的な条件です。希望校の募集要項を必ず確認してください。
- 海外の高等学校を卒業、または卒業見込みであること
- 一定期間の海外在住・就学経験があること(2年以上が目安)
※留学期間は2年以上とするところが一般的ですが、一部では3年以上を義務づけています。 - 帰国後2年未満であること
※多くの大学では「帰国後2年以内」。一部では「1年以内」など厳しめの条件もあります - 高校卒業時に18歳以上であること
提出書類(※大学により異なります)
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
在籍校が発行したもの。英文での提出が一般的。 - 成績証明書(Transcript)
高校在学中の全成績を記載した公式なもの。加点評価なども含まれる場合あり。 - 現地政府による統一試験の成績証明書
統一試験とは大学入学のための資格試験のことで、オーストラリアではVCE(ビクトリア州)、HSC(ニュー・サウス・ウェールズ州)など、ニュージーランドではNCEAレベル3と呼ばれるものです。ちなみに、アメリカであればSATまたはACT、イギリスであればGCSEおよびGCE(Aレベル)がこれにあたります。
※出願必須とする大学は全体の2割程度。提出「推奨」とする大学も多数。 - 英語能力試験のスコア
TOEFL iBT、IELTS、TOEICなど。
最近ではIELTS 5.5〜6.5以上やTOEFL iBT 45〜80以上を基準とする大学が多い。 - その他
- 志望理由書(エッセイ)
- 推薦状(学校・担任・指導教員など)
- 活動実績書(ボランティア・課外活動等)を求める大学も
帰国生入試までの流れ
志望校・専攻を明確にする
入試の準備に入る前に、まずは「自分が大学で何を学びたいのか」を明確にすること。そして、その分野を勉強するために、日本にはどんな大学や学部があるのかをしっかり調べましょう。
また、試験科目について調べることも忘れてはなりません。書類審査、英語、小論文、面接などが主なものですが、自分の得意分野もあるはずですから、そのあたりも重要なポイントです。すべり止めも含め、受験する大学は数校選んでおきましょう。
受験プランを練る
帰国生入試の受験に関する情報誌や資料を参考にして、受験資格、試験科目、入試日程、倍率などをチェックします。受験日が重なる可能性もあるので、過去のデータや実績をもとにして、優先順位を明確にしてスケジューリングしましょう。
志望校の願書を取り寄せる
本命からすべり止めまで、受験を希望する大学の受験要項・出願書類を取り寄せます。最近は大学公式サイトから募集要項をダウンロードまたは請求ができます。大学によっては、海外への送付を行わないところもありますので、その場合はいったん実家に送ってもらうように手配することになります。
出願の手続きをする
出願書類は大学によって異なりますが、一般的には卒業(見込み)証明書、成績証明書、統一試験の成績証明書、英語試験(TOEICやTOEFL、IELTSなど)のスコアなどです。大学によっては、推薦状を要求するところもあります。
志望校入試に向けた準備
帰国生入試の対策
帰国生入試で合格を勝ち取るには、英語・日本語の力をバランスよく磨くことが鍵です。
英語
帰国生であっても、日本の大学が出題する英語問題には特有の傾向があります。日本の大学の入試英語に数多く触れて、傾向を把握するようにしましょう。
小論文
小論文では、単なる知識よりも自分の意見を筋道立てて表現できるかが問われます。海外生活で得た視点を、日本語でどう伝えるかがカギ。自分の留学経験の中からテーマを選んで、文章にしてみることが大切です。また日本語から離れた生活をしていると、国語力が低下したり、日本語のリズムに疎くなってしまうこともあるので、新聞や時事ニュース、評論記事などを日常的に読み、日本語の語彙や論理展開に触れる習慣をつけるようにしましょう。
面接
帰国生入試の面接では、「なぜこの大学・学部なのか」、「どんな学びをしたいか」などが中心です。また、自分の留学経験をどう活かすか、という視点もよく問われます。自分の言葉でクリアに表現できるよう、事前にまとめておきましょう。