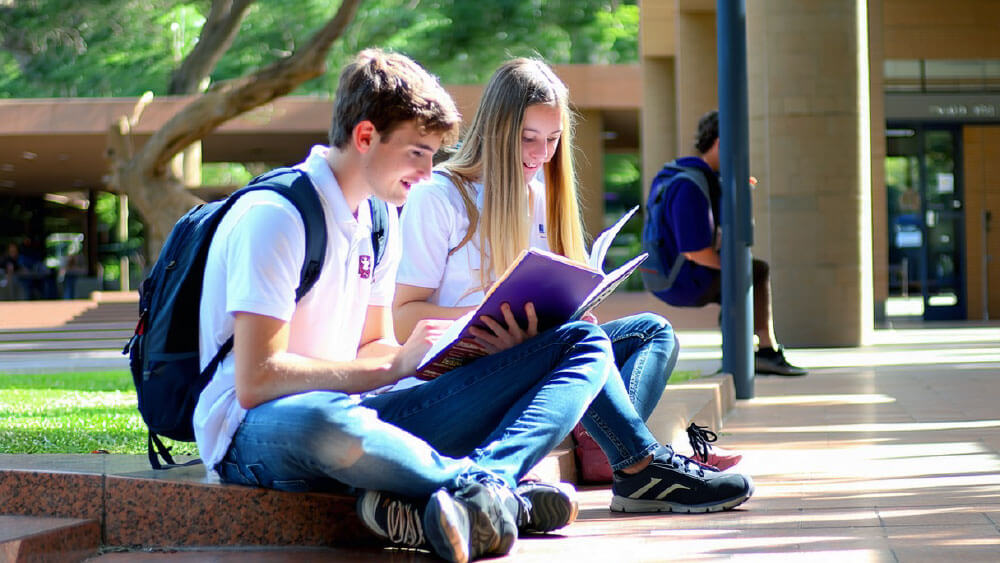G’day mate! 皆さんこんにちは、オーストラリアのクイーンズランド大学に大学留学していたジュンナです🐨
大学留学生活が終わり、日本での生活になってから気づけば1年半経ちました 。留学中は「毎日が挑戦」で必死に過ごしていましたが、帰国して時間が経つと、あの経験がただの思い出ではなく、今の自分の価値観や行動に深く根付いていることを実感します。留学直後、語学力や学業の成果よりも強く感じたのは、異文化で生き抜いた中で得た力や、帰国後に感じたリアルなギャップでした。今回は1年半たった今思うことの前編として、「留学で得たスキル」と「日本に戻って感じた逆カルチャーショック」を中心に振り返りたいと思います。
目次📌
1. 留学中に身について力とは?
「留学=英語力アップ」というイメージを持っている方は多いと思います。もちろん、語学は留学の大きな魅力の一つですが、実際にオーストラリアで数年間過ごしてみて感じたのは、語学力以上に「生き抜く力」や「頼る勇気」こそが、最大の学びだったということです。下記で、特に得てよかったと思う力を紹介します。
● 「自分の価値観」を相対化する力
留学を通して私が強く感じたのは、「正解はひとつじゃない」ということです。日本で育ってきた私は、どこかで「みんなが同じように行動するのが安心」と思っていました。でもオーストラリアに行くと、その考えがどんどん崩れていきました。たとえば、大学の授業中。日本の大学だと、教授が話している間は黙って聞くのが普通ですよね。ところがクイーンズランド大学では、学生が授業の途中で「ちょっと質問いいですか?」と手を挙げたり、時には教授の説明に「それは違うんじゃないか」と意見を返すこともありました。最初は「え、そんなに自由でいいの?」と驚きましたが、彼らにとっては積極的に参加することが学びの一部。私はそれまで「静かに聞く=礼儀」と思っていたけれど、「発言する=リスペクト」だという価値観に触れた瞬間でした。
また、時間の感覚も違いました。日本では「5分遅刻」でもすごく気にすることが多いですが、現地では友達との待ち合わせに10分、15分遅れてくるのはよくあること。最初は「なんでそんなにルーズなの?」と戸惑いましたが、彼らは「相手を待たせて申し訳ない」というより「焦らずに安全に来た方がいい」という考え方。時間に正確な日本の良さもあれば、オーストラリアのように「気持ちに余裕を持つ」考え方もあるのだと学びました。
こうした体験を通して得たのは、単なる「異文化理解」ではなく、「自分が当たり前と思っていたことを一歩引いて見られる力」です。今でも日本で働いていると「これって本当に絶対必要なルール?」と疑問を持てるようになり、柔軟な発想につながっています。
● 「頼る勇気」を持つ力
留学当初は「自分で全部やらなきゃ」と思い込んでいました。特に大学の課題は、日本語ですら苦戦するような内容を英語でこなさないといけないので、本当にプレッシャーが大きかったです。実際に、一度プレゼン準備で行き詰まり、2日間ほとんど寝ずに作業したことがありました。
そのとき思い切って、同じ授業を受けていたオーストラリア人の友人に相談してみました。すると「一緒に図書館でやろうよ!」と声をかけてくれて。私は「迷惑をかけるんじゃないか」と心配していましたが、友人にとっては「一緒に頑張ること」がむしろ自然なことだったのです。結果的に効率も上がり、何より「一人で抱え込まなくていいんだ」と安心しました。
それ以来、分からないことがあれば教授やチューターにメールしたり、友人に相談したりするように。頼ることは弱さではなく、信頼関係を築くための一歩だと学びました。日本で生活していたらなかなか身につかなかった力かもしれません。
● 「生活力」としてのサバイバルスキル
留学生活では、日本にいるときよりも「生活そのもの」と向き合う時間が増えます。私はシェアハウスに住んでいたのですが、光熱費の高さに驚きました。冬になると暖房を使いたいところですが、少し油断すると請求額が跳ね上がります。
そこで、シェアメイトたちと「なるべく暖房を使わないチャレンジ」を始めました。氷のように冷える部屋で、みんなで靴下を二重に履いたり、ホットウォーターボトルを作って寝たり。ちょっとしたサバイバルでしたが、「意外と工夫すればなんとかなる」という強さを身につけました。
さらに、自炊の工夫も生活力を高めるきっかけでした。外食は高いので、週末にまとめて安い食材をマーケットで買って、シェアメイトと一緒に料理。日本にいた頃は料理に苦手意識がありましたが、限られた予算の中で「どうすれば栄養をとれるか」「どうすれば飽きないか」を考えるうちに、自然と得意になっていきました。今でも「自炊力」は社会人生活で役立っています。
● 「楽しむこと」を見つける力ル
最後に私が一番留学で得られてよかったなと感じるスキルですが、それは「楽しむこと」を自分から見つける力です!留学生活は、想像以上に孤独やストレスがつきまといます。私も一時期、友人関係がうまくいかず、授業でも壁にぶつかり、心が折れそうになったことがありました。そんなとき、意識的に「小さな楽しみ」を作るようにしました。
例えば、週末に近所のカフェへ行き、日記を英語で書いてみたり、マーケットで知らない果物を買って味見してみたり。たったそれだけでも「今日は新しいことをした」という達成感が生まれました。特に印象に残っているのは、毎週末に開かれるファーマーズマーケットでの時間。珍しい野菜を買ってシェアメイトと料理したり、ライブ音楽を聴きながら朝食を食べたりするのが習慣になり、孤独感がぐっと和らぎました。「大きな成功」や「目に見える成果」がなくても、自分なりに楽しみを作れること。これは留学を生き抜くために欠かせないスキルでしたし、帰国後の今も「忙しい日常の中で小さな幸せを見つける」習慣につながっています。
2. 帰国後に感じた逆カルチャーショック

オーストラリアでの大学生活を終え、日本に帰国した時ちょっとしたカルチャーショックを感じました。巷でいう「逆カルチャーショック」と呼ばれる現象に私も陥ってしまい…留学先で当たり前だった価値観や行動が日本に戻るとギャップとして感じられました。
まず大きかったのは、人との距離感やコミュニケーションの違いでした。オーストラリアでは初対面の人でもフランクに会話を始めたり、少し雑談するだけで打ち解けることができます。しかし帰国後すぐ会社で働き始めたのもあったのですが、日本では初対面ではまず形式的な挨拶が求められ、雑談よりも必要な話だけをする場面が多く、フレンドリーに接しようとすると相手が戸惑ってしまうということもありました。
生活面で特に印象的だったのは、接客やサービスのフォーマルさです。オーストラリアではレストランやカフェの接客はカジュアルでフレンドリー。お客さんと会話を楽しむことも多く、笑顔でリラックスした雰囲気を作れます。しかし日本に帰国すると、どの飲食店やショップでも、挨拶や言葉遣い、立ち居振る舞いまでが非常に形式的で、最初は戸惑いというよりも「こんなにもかしこまってたっけ?」と感じたのが大きかったです。
さらに、日常生活の中でまだ現金の使用が多いことにも驚きました。オーストラリアではほとんどの支払いがカードやモバイル決済で完結し、現金を使う場面はほとんどありません。しかし日本では、コンビニや飲食店、さらには交通機関の一部でも現金が必要なことがあり、キャッシュレス中心に慣れていた私には新鮮な驚きでした。
ちなみに、実際に起きた珍事件をご紹介すると、まだ現金文化に慣れていなかった私はクレジットとカードだけを持って近くのたこ焼き屋さんに立ち寄りました。おいしいたこ焼きをおなか一杯食べて、さあ帰ろう!とお会計に行くとまさかの現金のみ!財布の中には10円しかなく一気に汗が出てきました…偶然にも近くに住んでいる友達が助けてくれ、その場はなんとかなりました!その時思ったのは、またもなお自分は当たり前という価値観に囚われていたのだと気づき、それからは財布の中にある小銭を定期的に管理したり、必要に応じてATMで現金を引き出すなど、日本独自の生活リズムに合わせていきました。
飲食店やカフェでも微妙な差を感じました。オーストラリアでは注文時に軽く会話を交わすだけで、笑顔で「ありがとう」と言えば十分でしたが、日本では「いらっしゃいませ」「少々お待ちください」といった決まり文句が丁寧に繰り返され、サービスのテンポも速く感じました。私はついオーストラリア流にお客さんと和やかに会話してしまい、店員さんや周囲の動きに合わせることが最初は大変でした。
こうした日常の細かい違いに最初は戸惑いましたが、オーストラリアで培った柔軟性や観察力が役立ちました。
▶まとめ
こうして日本に戻って最初の頃は、小さなことでも驚きや戸惑いの連続でしたが、オーストラリアで培った観察力や臨機応変さが役立つ場面も多くありました。日常のちょっとしたカルチャーショックも、今では笑い話に。次回の後編では、こうした経験が社会人生活や仕事にどう活きているのか、実際のエピソードとともに振り返っていきたいと思います。